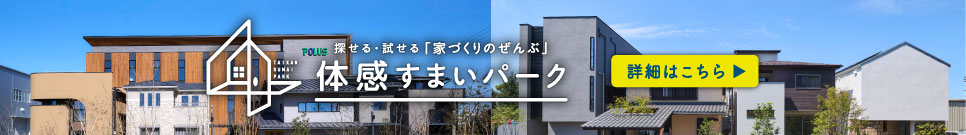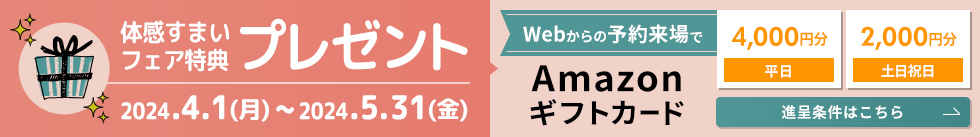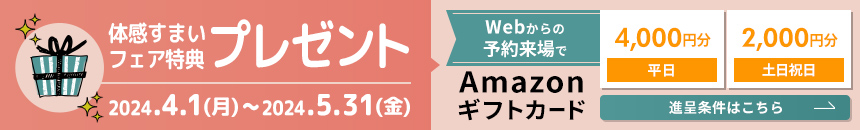Vol.75
公開日:2025年6月18日
更新日:2025年6月18日
耐震等級1・2・3の違いとは?等級を高めるポイントやメリットなど耐震の基礎を解説!
その他
地震大国の日本では、地震に強い家づくりが重要です。どのレベルの耐震等級にすればよいか、お悩みではないでしょうか。
本記事では、耐震等級のそれぞれのレベルの違いや等級を高めるポイント、メリットについてをまとめています
耐震等級についての基礎知識を知り、地震に強い家づくりの参考にしてください。
本記事では、耐震等級のそれぞれのレベルの違いや等級を高めるポイント、メリットについてをまとめています
耐震等級についての基礎知識を知り、地震に強い家づくりの参考にしてください。
▼目次
探せる・試せる「家づくりのぜんぶ」
体感すまいパーク
体感すまいパーク
体感すまいパークとは、ポラスの注文住宅5ブランドのモデルハウスが一度に見られる、ポラスの総合住宅展示場です。
リアルサイズで建てられたモデルハウスでは、機能や動線、素材などの住み心地を実際に体感できます。
お子さまも楽しめるイベントも随時開催中です。
体感すまいパークで理想のすまいを一緒に叶えましょう。
リアルサイズで建てられたモデルハウスでは、機能や動線、素材などの住み心地を実際に体感できます。
お子さまも楽しめるイベントも随時開催中です。
体感すまいパークで理想のすまいを一緒に叶えましょう。
そもそも耐震等級って何?
日本は過去に何度も大きな地震に見舞われ、甚大な被害を受けてきました。建物の強度は建築基準法などによって公的に基準が定められており、基準をもとに建物の耐震性の指標となっているのが「耐震等級」です。
耐震等級は、2000年4月1日施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく「住宅性能表示制度」における評価項目の一つです。
現在の住宅業界では、住まいの耐震性を示すものとして用いられています。
近い将来、南海トラフ地震、首都直下地震なども予想されており、これから家づくりに取り組むうえで非常に重要なポイントになります。
耐震等級は、2000年4月1日施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく「住宅性能表示制度」における評価項目の一つです。
現在の住宅業界では、住まいの耐震性を示すものとして用いられています。
近い将来、南海トラフ地震、首都直下地震なども予想されており、これから家づくりに取り組むうえで非常に重要なポイントになります。
耐震等級1
耐震等級1とは、建築基準法で定められている最低限の耐震性能を満たす水準です。下記を想定した性能となっています。
「倒壊・崩壊しない」は無傷ではなく、倒壊によって人命を失わないという意味です。住宅自体は補修や建て替えが必要になる恐れがあります。
- ・数百年に一度程度の地震(阪神・淡路大震災や熊本地震のような震度6強から7程度)に対して倒壊や崩壊をしない
- ・数十年に一度発生する地震(震度5程度)では住宅が損傷しない
「倒壊・崩壊しない」は無傷ではなく、倒壊によって人命を失わないという意味です。住宅自体は補修や建て替えが必要になる恐れがあります。
耐震等級2
耐震等級2は、等級1の1.25倍の地震に耐えられる性能・耐震強度の水準です。
「長期優良住宅」では、耐震等級2以上が認定の条件とされています。特に、災害時の避難所として指定されるような学校などの公共施設の場合は、耐震等級2以上の強度を持つことは必須となっています。
「長期優良住宅」では、耐震等級2以上が認定の条件とされています。特に、災害時の避難所として指定されるような学校などの公共施設の場合は、耐震等級2以上の強度を持つことは必須となっています。
耐震等級3
耐震等級1の1.5倍の耐震性を満たすのが耐震等級3です。「震度5強相当の1.5倍の力に対して倒壊・崩壊しない」程度の強度が基準となっています。
警察署や消防署などは、耐震等級3が必須となっています。現行の耐震性能ではもっとも高い基準です。
警察署や消防署などは、耐震等級3が必須となっています。現行の耐震性能ではもっとも高い基準です。
耐震基準との違い
耐震基準とは一定の強さに耐えられる建物の構造の基準のことで、耐震等級は耐震基準よりも高水準の耐震性能を評価する制度です。
耐震基準は、関東大震災の翌年の1924年に明文化されて以来、大きな震災があるごとに内容が見直されてきました。
1950年の建築基準法制定後は、耐震基準は1971年、1981年、2000年に大きな改正がおこなわれています。
耐震基準についてもっと知りたい方は下記記事をご覧ください。
>>新耐震基準、旧耐震基準とは?
耐震基準は、関東大震災の翌年の1924年に明文化されて以来、大きな震災があるごとに内容が見直されてきました。
1950年の建築基準法制定後は、耐震基準は1971年、1981年、2000年に大きな改正がおこなわれています。
耐震基準についてもっと知りたい方は下記記事をご覧ください。
>>新耐震基準、旧耐震基準とは?
熊本地震における耐震等級3の木造住宅
2016年4月に発生した熊本地震では4月14日及び16日に震度7の地震が2回観測されました。国土交通省「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書では、「旧耐震基準(昭和56年5月以前)の木造建築物の倒壊率は28.2%(214棟)に上っており、新耐震基準の木造建築物の倒壊率(昭和56年6月~平成12年5月:8.7%(76棟)、平成12年以降:2.2%(7棟))と比較して顕著に高かった」と記されています。
旧耐震と新耐震の被害の差は以下の考察がされています。
新耐震基準における耐震等級3の住宅は、2度大きな揺れに見舞われた熊本地震でも大部分に被害がありませんでした。これから起きることが懸念されている大地震に対しても安全性が期待できそうです。
木造住宅について更に詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
>>木造住宅のメリット・デメリットとは?
旧耐震と新耐震の被害の差は以下の考察がされています。
- ・新耐震基準は旧耐震基準の約1.4倍の壁量が確保されているため、倒壊率に顕著な差があった
- ・耐震等級3(倒壊等防止)の住宅は新耐震基準の約1.5倍の壁量が確保されており、該当する住宅は、大きな損傷が見られず、大部分が無被害であった
新耐震基準における耐震等級3の住宅は、2度大きな揺れに見舞われた熊本地震でも大部分に被害がありませんでした。これから起きることが懸念されている大地震に対しても安全性が期待できそうです。
木造住宅について更に詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
>>木造住宅のメリット・デメリットとは?
耐震等級を高めるポイント
建物の重さを軽くする
建物の重さは、建物の強度を算出する構造計算にも含まれている要素です。建物が重いほどそれを支える構造の強度を高める必要があります。
耐震等級を高くするためには、屋根を軽量化することが一つのポイントです。比較的重量のある瓦屋根よりは金属屋根のほうが軽く、構造へかかる負担も軽減されます。瓦屋根にする場合でも比較的軽量な防災瓦を選ぶのもおすすめです。
また外壁では、重いモルタルやタイルよりも軽いサイディングを採用すると耐震性の向上につながります。
耐震等級を高くするためには、屋根を軽量化することが一つのポイントです。比較的重量のある瓦屋根よりは金属屋根のほうが軽く、構造へかかる負担も軽減されます。瓦屋根にする場合でも比較的軽量な防災瓦を選ぶのもおすすめです。
また外壁では、重いモルタルやタイルよりも軽いサイディングを採用すると耐震性の向上につながります。
耐力壁の量を増やす
建物を支える構造としての壁を耐力壁といいます。建物の耐震性を高めるには、耐力壁の数を増やすことが大切です。例えば壁量が増える個室を1階に置き、壁の量の少ない開放的なリビングを2階に配置すると、耐震面では有利となります。
耐力壁の配置バランスを考える
地震の力が1か所に集中してしまうと、そこだけ負荷が大きくなり、損傷しやすくなります。なるべく家全体で均等に地震の力を受け止めるためにも、耐力壁はバランスよく配置することが重要です。
床の耐震性を高める
耐震性を高めるためには、床の面の強さも大きなポイントです。薄い床板だけでなく、強度の高い構造用合板などを床の下地に張ることで、柱や梁などの構造をしっかりと支えることができます。
耐震等級が高いメリット
大きな地震による損傷が小さい
耐震等級が高くなるにつれて、家の損傷が少なくなるため、震災後も避難所ではなくわが家に住み続けられる可能性も大きくなります。建て替えや補修にかかる費用も少なくなり、家族の不安も軽減できるはずです。
地震保険の「耐震等級割引」を受けられる
地震保険では耐震等級に応じて保険料の割引を受けることができます。割引率は下記のとおりです。
- 耐震等級1:10%
- 耐震等級2:30%
- 耐震等級3:50%
住宅ローンの金利優遇が受けられる
耐震等級が高くなるにつれて耐震性が増すことになるため、耐震等級3の場合には、住宅ローンの金利を優遇する金融機関もあります。
例えば、住宅金融支援機構の住宅ローン「【フラット35】S」では、耐震性を含む住宅性能のレベルによって、0.25%から0.5%も金利が下がる可能性があります(※2025年5月現在)」。
例えば、住宅金融支援機構の住宅ローン「【フラット35】S」では、耐震性を含む住宅性能のレベルによって、0.25%から0.5%も金利が下がる可能性があります(※2025年5月現在)」。
耐震性に強みを持つポラスの技術
構造計算を全棟で実施
地震や台風などの自然による外力を受けたときの安全性を計算する構造計算を、ポラスでは全棟で実施しています。
基礎から構造まで一貫して計算し、一棟ごとに力の伝わり方を精緻に把握して、適切な箇所に必要な部材を配置しています。
基礎から構造まで一貫して計算し、一棟ごとに力の伝わり方を精緻に把握して、適切な箇所に必要な部材を配置しています。
オリジナル構造計算ソフト「ウッド・イノベーターNEXT」
ポラスでは、オリジナル構造計算ソフト「ウッド・イノベーターNEXT」という独自の倒壊シミュレーションを全棟で実施しています。
実際に建てる家を3Dで再現して、実際に起きた大地震と同じ揺れに耐えることができるか、揺れに弱く、補強が必要な箇所はどこかを設計段階で確認できます。自由度の高いデザインを実現しながらも、耐震性も追求しています。
ウッド・イノベーターNEXTについてもっと知りたい方は下記動画をご覧ください。
>>ウッド・イノベーターNEXTをもっと見る
実際に建てる家を3Dで再現して、実際に起きた大地震と同じ揺れに耐えることができるか、揺れに弱く、補強が必要な箇所はどこかを設計段階で確認できます。自由度の高いデザインを実現しながらも、耐震性も追求しています。
ウッド・イノベーターNEXTについてもっと知りたい方は下記動画をご覧ください。
>>ウッド・イノベーターNEXTをもっと見る
加工実績日本一のプレカット工場
木造住宅の構造を支える柱や梁などの木材も、その強度と品質がばらつきなく高いレベルで供給されていることが重要です。
ポラスでは、自社のプレカット工場で精度の高い木材加工にこだわり、木造ならではの粘り強い構造を実現しています。
ポラスでは、自社のプレカット工場で精度の高い木材加工にこだわり、木造ならではの粘り強い構造を実現しています。
ポラス建築技術訓練校
ポラスでは家づくりの過程で一貫して自社で責任をもって全うする、「一貫施工体制」を確立しています。
また、「ポラス建築技術訓練校」を設立し、現場で働きながら知識や技術を学ぶことができる環境を整えています。
>>ポラスの大工についてはこちら
ポラスの家づくりについては、モデルハウスやポラスの総合住宅展示場「体感すまいパーク」に足を運んでみると、もっと詳しい情報を得ることができます。ぜひ一度、体感すまいパークや展示場でご自身の目で確かめてみてください。
>>ポラスの住宅展示場を探す
>>体感すまいパークについてはこちら
また、「ポラス建築技術訓練校」を設立し、現場で働きながら知識や技術を学ぶことができる環境を整えています。
>>ポラスの大工についてはこちら
ポラスの家づくりについては、モデルハウスやポラスの総合住宅展示場「体感すまいパーク」に足を運んでみると、もっと詳しい情報を得ることができます。ぜひ一度、体感すまいパークや展示場でご自身の目で確かめてみてください。
>>ポラスの住宅展示場を探す
>>体感すまいパークについてはこちら
耐震等級が高いデメリット
耐震等級の基礎を知っておこう!
希望の耐震等級を設定する
耐震等級は、最低基準の耐震等級1以上であれば、施主が自分で希望を設定できます。耐震性を高めようとするためには、コストや間取りへの影響も生じます。
家づくりにあたっての優先順位や希望の条件などを検討して、等級を選ぶようにしたいものです。
家づくりにあたっての優先順位や希望の条件などを検討して、等級を選ぶようにしたいものです。
耐震等級の取得は必須ではない
耐震等級などの住宅性能表示制度は、義務ではなく、任意で評価を受け評価書を発行してもらうものであるため、建物の建築時には建築基準法を遵守していれば住宅は建てられます。
耐震等級の認定を受けるには第三者機関の「登録住宅性能評価機関」による住宅性能の評価が必要です。認定を受けていなくとも、構造計算によって基準を満たす耐震性能がある場合は、「耐震等級〇相当」という表現をする場合もあります。
耐震等級の認定を受けるには第三者機関の「登録住宅性能評価機関」による住宅性能の評価が必要です。認定を受けていなくとも、構造計算によって基準を満たす耐震性能がある場合は
依頼の段階で希望の耐震等級などを伝える必要がある
注文住宅を新築する場合には、まず設計の段階で希望の耐震等級を決めることが重要です。
営業や設計の担当者とどの等級にするか話し合い、早い段階で要望を伝えることで、無駄の少ないスムーズな家づくりが可能になります。
営業や設計の担当者とどの等級にするか話し合い、早い段階で要望を伝えることで、無駄の少ないスムーズな家づくりが可能になります。
耐震等級の認定・性能評価を受ける方法
耐震等級の評価の流れ
家づくりの際、耐震等級の認定・性能評価を受けるには、国土交通大臣に任命・監督されている第三者機関に住宅性能評価の審査を依頼しなければなりません。
評価の流れは上記のとおりです。
まず、設計性能評価の申請をおこない、評価を受けます。評価書が交付された後着工となります。
工事中には建設性能評価の申請をおこない、検査を受けます。その後、評価書の交付を受け、引渡しとなります。
評価の流れは上記のとおりです。
まず、設計性能評価の申請をおこない、評価を受けます。評価書が交付された後着工となります。
工事中には建設性能評価の申請をおこない、検査を受けます。その後、評価書の交付を受け、引渡しとなります。
耐震等級の評価にかかる費用
住宅性能評価を依頼するときにかかる費用は、第三者機関によって異なります。およそ10万円~15万円が一般的です。
耐震等級の認定は任意であるため、もし住宅性能評価書が不要であるなら、費用をかけて審査を受ける必要はありません。
耐震等級の認定は任意であるため、もし住宅性能評価書が不要であるなら、費用をかけて審査を受ける必要はありません。
耐震技術に強みがあるポラスの家づくり
ポラスでは、「一貫施工体制」のもと、構造計算や耐震シミュレーション「ウッド・イノベーターNEXT」を全棟実施し、精度の高い加工を施した高品質な木材で地震に強い家づくりに取り組んでいます。
その他、外壁と構造躯体の⼀体化で建物の変形を抑え、繰り返しの地震にも耐える「ダブルモノコック構造」、家に加わる地震動エネルギーを熱エネルギーに変換‧吸収して建物の揺れを防ぐ「Endure Wall」、天井裏と桁間にも⾼性能グラスウールを敷き込んだ⼆重断熱⼯法「天井断熱⼯法Bit-e」など、耐震性のほか、断熱性・耐久性も兼ね備えたポラスの技術力でお客さまに安心した住宅をご提供しています。
>>ウッド・イノベーターNEXTの詳細はこちら
>>ポラスの耐震性についてはこちら
>>ポラスの大工についてはこちら
耐震性、デザイン、コストをバランスよく考慮し、プランに反映させることで、ご家族が末永く安心・安全・快適に暮らせる住まいを長年の間、数多く手がけてきました。ポラスの技術力を、ぜひ住宅展示場や体感すまいパークで確認してみてください。
耐震性についてご不明な点は展示場の営業担当者にお気軽にご相談ください。
>>ポラスの住宅展示場を探す
>>体感すまいパークについてはこちら
その他、外壁と構造躯体の⼀体化で建物の変形を抑え、繰り返しの地震にも耐える「ダブルモノコック構造」、家に加わる地震動エネルギーを熱エネルギーに変換‧吸収して建物の揺れを防ぐ「Endure Wall」、天井裏と桁間にも⾼性能グラスウールを敷き込んだ⼆重断熱⼯法「天井断熱⼯法Bit-e」など、耐震性のほか、断熱性・耐久性も兼ね備えたポラスの技術力でお客さまに安心した住宅をご提供しています。
>>ウッド・イノベーターNEXTの詳細はこちら
>>ポラスの耐震性についてはこちら
>>ポラスの大工についてはこちら
耐震性、デザイン、コストをバランスよく考慮し、プランに反映させることで、ご家族が末永く安心・安全・快適に暮らせる住まいを長年の間、数多く手がけてきました。ポラスの技術力を、ぜひ住宅展示場や体感すまいパークで確認してみてください。
耐震性についてご不明な点は展示場の営業担当者にお気軽にご相談ください。
>>ポラスの住宅展示場を探す
>>体感すまいパークについてはこちら