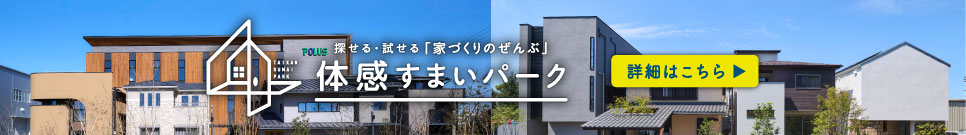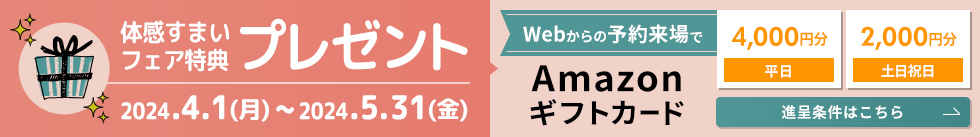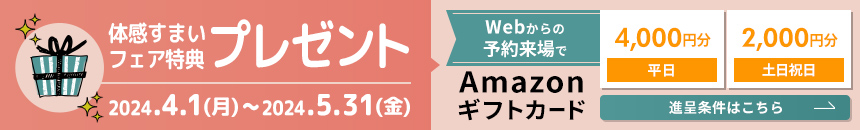Vol.73
公開日:2025年4月14日
更新日:2025年4月14日
木造住宅のメリット・デメリットとは?工法や耐震性・寿命を解説!
その他
日本の住宅の多くを占めている木造住宅ですが、鉄骨や鉄筋コンクリートとの耐震性や寿命の違いが気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、木造住宅の特徴やメリット・デメリット、ポラスの木造住宅についてまとめています。
木造住宅の基礎知識を知り、家づくりの参考にしてください。
本記事では、木造住宅の特徴やメリット・デメリット、ポラスの木造住宅についてまとめています。
木造住宅の基礎知識を知り、家づくりの参考にしてください。
▼目次
探せる・試せる「家づくりのぜんぶ」
体感すまいパーク
体感すまいパーク
体感すまいパークとは、ポラスの注文住宅5ブランドのモデルハウスが一度に見られる、ポラスの総合住宅展示場です。
リアルサイズで建てられたモデルハウスでは、機能や動線、素材などの住み心地を実際に体感できます。
お子さまも楽しめるイベントも随時開催中です。
体感すまいパークで理想のすまいを一緒に叶えましょう。
リアルサイズで建てられたモデルハウスでは、機能や動線、素材などの住み心地を実際に体感できます。
お子さまも楽しめるイベントも随時開催中です。
体感すまいパークで理想のすまいを一緒に叶えましょう。
木造住宅ってどのような家?
特徴
木材を主な構造に用いた住まいを「木造住宅」と総称します。古来、日本では伝統的に木材を使った住まいが建てられてきました。国土の約8割が森林ということもあり、もっとも手軽に利用できる素材であったためです。
現在は新設住宅着工戸数のうち一戸建ての建築構造は約9割が木造住宅となっています。※林野庁「令和5年森林・林業白書」参照
脱炭素社会の実現に向けた取り組みが世界規模で進んでおり、日本でも建物の木造化を促進する傾向になっています。
現在は新設住宅着工戸数のうち一戸建ての建築構造は約9割が木造住宅となっています。※林野庁「令和5年森林・林業白書」参照
脱炭素社会の実現に向けた取り組みが世界規模で進んでおり、日本でも建物の木造化を促進する傾向になっています。
木材の種類
日本で木造住宅に用いられる木は、スギやヒノキ、アカマツなどの針葉樹、ナラやケヤキ、ブナなどの広葉樹に大別されます。
針葉樹は速く成長し、加工しやすい特徴があることから日本各地で植林が進み、主に家の柱や梁に使われています。
一方、広葉樹は人の手が入っていない里山に多く広がっています。成長が針葉樹より遅い分、年輪の詰まった硬くて丈夫な材質が特徴で、家具やフローリングなどに利用されています。
針葉樹は速く成長し、加工しやすい特徴があることから日本各地で植林が進み、主に家の柱や梁に使われています。
一方、広葉樹は人の手が入っていない里山に多く広がっています。成長が針葉樹より遅い分、年輪の詰まった硬くて丈夫な材質が特徴で、家具やフローリングなどに利用されています。
木造住宅の寿命
法律上、建物には構造ごとに「耐用年数」が定められています。木造住宅の法定耐用年数は22年、鉄骨造は鉄骨の厚さごとに19年〜34年、鉄筋コンクリート造は47年となっています。一見、長持ちしないような印象を持たれてしまうかもしれませんが、
木造住宅の場合、傷んだ部位は交換できます。必要なメンテナンス・リフォームを施すことで住宅を長く保たせることも可能です。
断熱性、耐震性など住宅の基本性能を考慮して設計・施工した木造住宅であれば、安心・安全で、末長く快適に住み続けることもできます。
木造住宅の場合、傷んだ部位は交換できます。必要なメンテナンス・リフォームを施すことで住宅を長く保たせることも可能です。
断熱性、耐震性など住宅の基本性能を考慮して設計・施工した木造住宅であれば、安心・安全で、末長く快適に住み続けることもできます。
木造住宅の建築方法と工法
木造軸組工法(在来工法)
柱や梁を組み合わせて枠組みをつくる、伝統的な住まいの工法を「木造軸組工法」(在来工法)といいます。壁ではなく軸組で支えるため、壁を設ける場所の選択肢が多く、さまざまな間取りに対応可能です。また、大きな窓を設けることもできます。
2×4(ツーバイフォー)工法、2×6(ツーバイシックス)工法
約2インチ×約4インチ(2×4)材、約2インチ×約6インチ(2×6)材と合板を主な構造材としており、床や壁などの「面」で建物を支える工法です。建築基準法では「枠組壁工法」とも言います。構造が箱のようにしっかり組まれるため、間取りの自由度はやや低くなりますが、耐震性が高くなるメリットがあります。
木造・鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄骨造(S造)はどう違う?
| 特徴 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| 木造住宅 | 木材を用いる。 多くの⼀軒家やアパートで採用。 |
コストが低い。 間取りの自由度が高い。 |
耐久性が低い。 防音性・気密性が低い。 |
| 鉄骨造 (S造) |
骨組みに鉄を用いる。 鋼材の厚さ6mm以上:重量鉄骨造 鋼材の厚さ6mm未満:軽量鉄骨造 |
構造材が軽く強い。 広い空間が実現可能。 |
耐火性が低い。 防音性・断熱性が低い。 |
| 鉄筋コンクリート造 (RC造) |
鉄筋とコンクリートを用いる。 | 耐久性が高い。 遮音性・断熱性が高い。 |
施工期間が長い。 費用が高い。 |
住宅は木造のほか、鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造(S造)の工法も用いられます。上記の表にそれぞれの特徴をまとめました。
・鉄筋コンクリート造(RC造):鉄筋とコンクリートを組み合わせた「鉄筋コンクリート造=RC(Reinforced Concrete)造」は、木造や鉄骨造と比べ、遮音性や断熱性が非常に高い点が特徴です。
・鉄骨造(S造):材料の「鋼材=Steel」の頭文字をとって、「S造」とも呼ばれます。構造材が軽く強いことから、木造よりも広い空間や大きな開口部をつくることも可能です。
木造、鉄筋コンクリート造、それぞれ長所と短所があります。ハウスメーカーや工務店によって得意とする工法が異なるため、それぞれの特徴をあらかじめ知っておきましょう。
木造住宅のメリット
建築コストが低い
木造住宅は他の工法よりも建築資材の木材が安価であることから、建築コストを比較的安くまとめることができます。
例えば、鉄骨造では、あらかじめ構造材に耐火処理や防錆処理を施す必要がありますが、木造では木材の種類や厚みによってある程度の耐火効果が見込まれているため、下処理が少なくてすむメリットがあります。
また、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比べて構造体が軽いため、基礎工事にあまり手間がかからず、土地の改良費用なども抑えやすいです。
令和6年の「建築着工統計調査」(国土交通省)によれば、一戸建て住宅総計の1㎡あたりの平均工事予定額23万円に対して、木造22万円、鉄骨造34万円、鉄筋コンクリート造39万円となっています。
例えば、鉄骨造では、あらかじめ構造材に耐火処理や防錆処理を施す必要がありますが、木造では木材の種類や厚みによってある程度の耐火効果が見込まれているため、下処理が少なくてすむメリットがあります。
また、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比べて構造体が軽いため、基礎工事にあまり手間がかからず、土地の改良費用なども抑えやすいです。
令和6年の「建築着工統計調査」(国土交通省)によれば、一戸建て住宅総計の1㎡あたりの平均工事予定額23万円に対して、木造22万円、鉄骨造34万円、鉄筋コンクリート造39万円となっています。
調湿効果があり乾燥対策ができる
木材は、空気中の湿度が高いときには水分を吸い込み、乾燥してくると水分を吐き出すという調湿効果を発揮します。
木造をふんだんに生かした住宅であれば、湿気の多い時期でもほどよく湿度が調整され、暖房を使う冬場も乾燥しにくくなります。季節によって気温や湿度が大きく変化する日本に適した工法・構造だといえます。
木造をふんだんに生かした住宅であれば、湿気の多い時期でもほどよく湿度が調整され、暖房を使う冬場も乾燥しにくくなります。季節によって気温や湿度が大きく変化する日本に適した工法・構造だといえます。
デザインの自由度が高い
木造軸組工法の場合、構造は柱や梁などで支えているため、窓や壁の配置の自由度が高く、間取りの制限は小さいといえます。将来の間取り変更も、比較的自由が利きます。自由設計に向いた工法です。
性能に関するメリット
耐震性があり地震に強い
阪神大震災のときに古い木造家屋が倒壊したニュースが報道されたため、木造は地震に弱いイメージを持っている方もいるかもしれません。鉄骨造よりも地震の力を構造全体でやわらかく受け流すため、耐震性には優れています。
大きな地震があるたびにその被災状況をもとに建築基準法などが見直され、必要な改正がおこなわれてきました。基礎を補強する、壁に筋交いを入れる、柱の接合部に金具を付けるなど耐震性を高める工夫も開発されています。
品確法に基づく耐震等級では、数百年に一度程度の地震(震度6強から7程度)に対しても倒壊・崩壊しない強さを等級1とし、最上位の等級3では等級1の1.5倍の地震力に耐える強さがある基準になっています。
ポラスではオリジナル構造計算ソフト「ウッド・イノベーターNEXT」を開発し、建てる前に大地震を想定した3Dシミュレーションで検証を実施しています。また、オリジナルの構造「ダブルモノコック」を開発し、地震に強い家づくりを実現しています。
>>ポラスの耐震性についてはこちら
耐震性について更に知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
>>新耐震基準、旧耐震基準とは?
また、耐震等級についても併せて詳細をご覧ください。
>>耐震等級1・2・3の違いとは?
大きな地震があるたびにその被災状況をもとに建築基準法などが見直され、必要な改正がおこなわれてきました。基礎を補強する、壁に筋交いを入れる、柱の接合部に金具を付けるなど耐震性を高める工夫も開発されています。
品確法に基づく耐震等級では、数百年に一度程度の地震(震度6強から7程度)に対しても倒壊・崩壊しない強さを等級1とし、最上位の等級3では等級1の1.5倍の地震力に耐える強さがある基準になっています。
ポラスではオリジナル構造計算ソフト「ウッド・イノベーターNEXT」を開発し、建てる前に大地震を想定した3Dシミュレーションで検証を実施しています。また、オリジナルの構造「ダブルモノコック」を開発し、地震に強い家づくりを実現しています。
>>ポラスの耐震性についてはこちら
耐震性について更に知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
>>新耐震基準、旧耐震基準とは?
また、耐震等級についても併せて詳細をご覧ください。
>>耐震等級1・2・3の違いとは?
断熱性があり暑さ・寒さ対策ができる
木材は乾燥すると鉄やコンクリートより熱を通しにくい性質があります。さらに断熱材を巡らし、気密シートなどで気密性を高めることで、高気密・高断熱の住まいが可能になります。
高気密・高断熱住宅についてもっと知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
>>子育てグリーン住宅支援事業とは? 条件となる高気密高断熱住宅についても解説!
ポラスでは一般のグラスウールより繊維の細かい「高性能グラスウール」や天井に二重断熱工法「Bit-e」、季節ごとに日差しを効率的に取り込む「Low-eガラス」の窓などを採用しており、断熱性の高い木造住宅を建てることができます。
>>ポラスの断熱性についてはこちら
高気密・高断熱住宅についてもっと知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
>>子育てグリーン住宅支援事業とは? 条件となる高気密高断熱住宅についても解説!
ポラスでは一般のグラスウールより繊維の細かい「高性能グラスウール」や天井に二重断熱工法「Bit-e」、季節ごとに日差しを効率的に取り込む「Low-eガラス」の窓などを採用しており、断熱性の高い木造住宅を建てることができます。
>>ポラスの断熱性についてはこちら
耐火性が備わっている
火に弱い印象をもたれがちな木造ですが、一定以上の太さがあれば、表面が炭化して内部が燃えるまで時間がかかる特徴があります。また火災が延焼しやすい住宅密集地域では、必要な防火措置を設けることが法律で義務づけられています。
木造工法のデメリット
耐用年数が短い
木造住宅の法定耐用年数は22年で他の構造・工法よりも短いです。
しかし、法定耐用年数は資産価値を算出する基準であり、実際の家の寿命、耐久性と直接の関係はありません。定期的に点検をおこない、傷みが進行する前に早めのメンテナンスを実施することで長く住むことも十分に可能です。
しかし、法定耐用年数は資産価値を算出する基準であり、実際の家の寿命、耐久性と直接の関係はありません。定期的に点検をおこない、傷みが進行する前に早めのメンテナンスを実施することで長く住むことも十分に可能です。
シロアリなど害虫のリスクがある
木造ならではのリスクがシロアリやキクイムシなどの害虫による被害です。こうした害虫は湿気を好むため、水回りの床下などに潜み、柱などを食い荒らして構造の強度を大幅に低下させてしまう恐れがあります。
新築時に必要な薬剤処理をおこなうほか、引渡し後は定期的に構造を点検してもらうことで、早期に駆除することが大切です。
新築時に必要な薬剤処理をおこなうほか、引渡し後は定期的に構造を点検してもらうことで、早期に駆除することが大切です。
職人によって仕上がりが変わる
木造の場合、現場での加工も多く、他の工法に比べて施工品質にばらつきが生じやすいという面があります。木材の品質、大工の加工技術によっても仕上がりが大きく左右されます。
施工会社の職人の腕を見極めることは難しいですが、工事中に現場に足を運び自分の目で確かめることはできます。気になることは遠慮せずに伝えましょう。
現在、職人の高齢化や職人不足問題により、日本の伝統的な木造住宅建築の技術継承は危機的状況にあります。ポラスでは、職人の地位向上に寄与し、腕の良い職人集団を後世に残していく「Design&Quality大工制度」を導入しています。技術を磨き続けるポラスの大工が高品質・高性能な家づくりの根幹を支えています。
また、ポラスでは1987年に「ポラス建築技術訓練校」を設立し、次世代を担う職人の育成に力を入れています。現場で働きながら学ぶ体制が整えられており、知識だけでなく技術も日々身につけています。
>>ポラスの大工についてはこちら
ポラスの大工がつくる高品質・高性能な家は、実際に住宅展示場で見ることができます。
>>ポラスの住宅展示場を探す
施工会社の職人の腕を見極めることは難しいですが、工事中に現場に足を運び自分の目で確かめることはできます。気になることは遠慮せずに伝えましょう。
現在、職人の高齢化や職人不足問題により、日本の伝統的な木造住宅建築の技術継承は危機的状況にあります。ポラスでは、職人の地位向上に寄与し、腕の良い職人集団を後世に残していく「Design&Quality大工制度」を導入しています。技術を磨き続けるポラスの大工が高品質・高性能な家づくりの根幹を支えています。
また、ポラスでは1987年に「ポラス建築技術訓練校」を設立し、次世代を担う職人の育成に力を入れています。現場で働きながら学ぶ体制が整えられており、知識だけでなく技術も日々身につけています。
>>ポラスの大工についてはこちら
ポラスの大工がつくる高品質・高性能な家は、実際に住宅展示場で見ることができます。
>>ポラスの住宅展示場を探す
防音性が低い
木造住宅では、音や振動に対して木材が共鳴する性質があるとともに、通気性が高いため、防音・遮音性が低くなる傾向があります。
交通騒音を防ぐ、ピアノを弾きたいなどの場合、 外壁と内壁の間に断熱材や気密シートを充てんする、壁そのものを厚くする、二重構造の壁や窓、床組を採用するなどの対策が可能です。
交通騒音を防ぐ、ピアノを弾きたいなどの場合、 外壁と内壁の間に断熱材や気密シートを充てんする、壁そのものを厚くする、二重構造の壁や窓、床組を採用するなどの対策が可能です。
ポラスの木造住宅の魅力
ポラスでは魅力ある木造住宅をつくるため、独自の技術やシステムを開発し、常に品質を高める姿勢を大切にしています。
現在、ポラスの家づくりでは、研究、設計、施工、アフターサポートまで、多くの工程を自社で責任を持って家を仕上げる「一貫施工体制」を確立しています。大工もプレカット工場も開発・研究施設も自社で持っている点が大きな強みです。
>>ポラスの特長はこちら
オリジナル開発の耐震検証システム「ウッド・イノベーターNEXT」や耐震性の高い「ダブルモノコック構造」、快適で省エネにも貢献する断熱技術「天井断熱⼯法Bit-e」なども、耐震性・断熱性・耐久性を兼ね備えたポラス独自の技術力です。ポラスの注文住宅では断熱等性能等級5を標準的にクリアしています。
さらに床下の湿気を防ぐ「ベタ基礎全周換気システム」、躯体腐食を防⽌する壁内通気システム、最長60年の点検・長期保証などによって、長年の経年劣化と自然災害による変形から住まいを守る耐久技術にも力を入れています。
>>ポラスの技術力はこちら
住宅の性能は実際に見て確かめることが大切です。ポラスの家づくりについてもっと知りたい方は、ポラスの総合住宅展示場「体感すまいパーク」の見学をおすすめします。ポラスの注文住宅5ブランドのモデルハウスが一度に見られる総合住宅展示場で、人気のデザイン、家事動線や素材の肌触り、土地探しなど「家づくりのぜんぶ」を探して試せる施設になっています。
>>体感すまいパークについてはこちら
>>ポラスの住宅展示場を探す
現在、ポラスの家づくりでは、研究、設計、施工、アフターサポートまで、多くの工程を自社で責任を持って家を仕上げる「一貫施工体制」を確立しています。大工もプレカット工場も開発・研究施設も自社で持っている点が大きな強みです。
>>ポラスの特長はこちら
オリジナル開発の耐震検証システム「ウッド・イノベーターNEXT」や耐震性の高い「ダブルモノコック構造」、快適で省エネにも貢献する断熱技術「天井断熱⼯法Bit-e」なども、耐震性・断熱性・耐久性を兼ね備えたポラス独自の技術力です。ポラスの注文住宅では断熱等性能等級5を標準的にクリアしています。
さらに床下の湿気を防ぐ「ベタ基礎全周換気システム」、躯体腐食を防⽌する壁内通気システム、最長60年の点検・長期保証などによって、長年の経年劣化と自然災害による変形から住まいを守る耐久技術にも力を入れています。
>>ポラスの技術力はこちら
住宅の性能は実際に見て確かめることが大切です。ポラスの家づくりについてもっと知りたい方は、ポラスの総合住宅展示場「体感すまいパーク」の見学をおすすめします。ポラスの注文住宅5ブランドのモデルハウスが一度に見られる総合住宅展示場で、人気のデザイン、家事動線や素材の肌触り、土地探しなど「家づくりのぜんぶ」を探して試せる施設になっています。
>>体感すまいパークについてはこちら
>>ポラスの住宅展示場を探す
木造住宅のメリット・デメリットを知って、理想の住まいにしよう!
木造住宅は日本の風土に適した形で発展してきた住まいです。鉄骨造やRC造など他の工法と比較したときにメリットもデメリットもありますが、それらの特徴をよく理解したうえで家づくりにのぞめば、十分に納得のいく選択肢になるはずです。
ポラスでは、木造住宅について55年以上の実績と経験があります。独自の技術や体制によって快適な住まいをご提供しているため、ぜひ一度、展示場やモデルハウスに足を運び、ご自分の目で確かめてみてください。
>>体感すまいパークについてこちら
>>ポラスの住宅展示場を探す
ポラスでは、木造住宅について55年以上の実績と経験があります。独自の技術や体制によって快適な住まいをご提供しているため、ぜひ一度、展示場やモデルハウスに足を運び、ご自分の目で確かめてみてください。
>>体感すまいパークについてこちら
>>ポラスの住宅展示場を探す