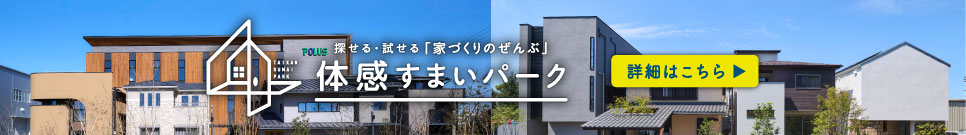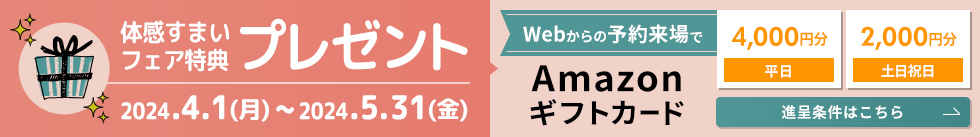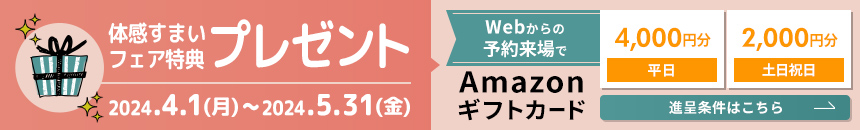Vol.77
公開日:2025年9月1日
更新日:2025年9月1日
吹き抜けのメリット・デメリットって?実例から、後悔しないためのポイントも解説
建築実例
注文住宅ならではの空間といえば吹き抜けです。リビングや玄関の頭上にゆったりと広がる吹き抜けに憧れる方も多いでしょう。
一方で、「吹き抜けのある家には憧れるけれども、冷暖房の効率が悪いのでは?」「耐震性は大丈夫?」といった不安を持っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、吹き抜けのメリットとデメリット、そして暮らしを快適なものにする吹き抜けの上手な工夫などについてご紹介します。
一方で、「吹き抜けのある家には憧れるけれども、冷暖房の効率が悪いのでは?」「耐震性は大丈夫?」といった不安を持っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、吹き抜けのメリットとデメリット、そして暮らしを快適なものにする吹き抜けの上手な工夫などについてご紹介します。
▼目次
探せる・試せる「家づくりのぜんぶ」
体感すまいパーク
体感すまいパーク
体感すまいパークとは、ポラスの注文住宅5ブランドのモデルハウスが一度に見られる、ポラスの総合住宅展示場です。
リアルサイズで建てられたモデルハウスでは、機能や動線、素材などの住み心地を実際に体感できます。
お子さまも楽しめるイベントも随時開催中です。
体感すまいパークで理想のすまいを一緒に叶えましょう。
リアルサイズで建てられたモデルハウスでは、機能や動線、素材などの住み心地を実際に体感できます。
お子さまも楽しめるイベントも随時開催中です。
体感すまいパークで理想のすまいを一緒に叶えましょう。
そもそも「吹き抜け」とは?
吹き抜けのメリット
吹き抜けがあることで、どのようなメリットがもたらされるのでしょうか。
主なポイントを以下にまとめました。プランニングの際に意識してみると、設計担当者との打ち合わせもよりスムーズに進むかもしれません。
主なポイントを以下にまとめました。プランニングの際に意識してみると、設計担当者との打ち合わせもよりスムーズに進むかもしれません。
室内の開放感が高まる
吹き抜けを設けることで頭上の空間が豊かに広がり、開放感が高まるというのは、大きなメリットです。
視界いっぱいに広がる吹き抜け空間は、住まいの見せ場の一つになります。家族が集まりたくなる空間の広がりをもたらし、来客をもてなす自慢のスペースとなるでしょう。
視界いっぱいに広がる吹き抜け空間は、住まいの見せ場の一つになります。家族が集まりたくなる空間の広がりをもたらし、来客をもてなす自慢のスペースとなるでしょう。
室内が明るくなる
吹き抜けがあると、高い位置に窓をつくりやすくなります。
一般的に、天井に設ける天窓は通常の窓の3倍の採光量があるといわれていますが、吹き抜け上部の高窓にも同様の明るさをもたらす効果が期待できます。近隣が密集した住宅地でも、室内に十分な自然光を導く手段として有効です。
一般的に、天井に設ける天窓は通常の窓の3倍の採光量があるといわれていますが、吹き抜け上部の高窓にも同様の明るさをもたらす効果が期待できます。近隣が密集した住宅地でも、室内に十分な自然光を導く手段として有効です。
風通しがよく、空気が循環しやすくなる
吹き抜けによって空間の高低差が大きくなると、室内の空気に温度差による対流が起きやすくなります。
吹き抜けの高窓を開閉できるようにしたり、シーリングファンを取り付けたりすると室内の空気に流れが生まれ、通風や換気の効果が期待できるようになります。
吹き抜けの高窓を開閉できるようにしたり、シーリングファンを取り付けたりすると室内の空気に流れが生まれ、通風や換気の効果が期待できるようになります。
家族間でコミュニケーションがとりやすくなる
吹き抜けは上下階で家族の気配をやりとりする場にもなります。複数のフロアをひと続きにする吹き抜けがあると、家族の声が届きやすくなり、お互いに何をしているのかがなんとなく伝わるようになります。
また、リビング階段などを組み合わせ、お互いに顔を見合わせる機会を増やすことで、コミュニケーションを活発にすることもできます。
また、リビング階段などを組み合わせ、お互いに顔を見合わせる機会を増やすことで、コミュニケーションを活発にすることもできます。
スキップフロアが作れる
スキップフロアとは、同じ空間のなかで一部の床の高さを変えた場所のことです。
吹き抜けがあると空間に高さの余裕があるので、半階ずらしたスペースを設けて立体的に空間を活用することも容易になります。1階と2階の中間領域ができることで、暮らしに新鮮な眺めと豊かな選択肢が生まれるでしょう。
吹き抜けがあると空間に高さの余裕があるので、半階ずらしたスペースを設けて立体的に空間を活用することも容易になります。1階と2階の中間領域ができることで、暮らしに新鮮な眺めと豊かな選択肢が生まれるでしょう。
吹き抜けのデメリットと対処方法
吹き抜けのメリットだけでなく、注意点やデメリットについても理解しておきたいものです。必要な対処をしておけば、より満足できる仕上がりになるでしょう。
室温や空調の調整がしづらい
吹き抜けのある部屋は空間が広いため、冷暖房が全体にいきわたるまでに時間とエネルギーが必要です。暖かい空気は天井付近に、冷たい空気は足元にたまりやすく、特に冬場は寒いと感じる人もいます。
これを防ぐためには、家全体の断熱性を高めることが大切です。断熱性が向上すれば、室内の温度差が小さくなり、熱が上階や寒い部屋に逃げにくくなります。
これを防ぐためには、家全体の断熱性を高めることが大切です。断熱性が向上すれば、室内の温度差が小さくなり、熱が上階や寒い部屋に逃げにくくなります。
メンテナンスがしづらい
天井が高くなると、高窓や照明器具など、手の届きにくい場所が増え、メンテナンスが困難になることがあります。
これを防ぐためには、メンテナンスを考慮して、脚立で届く位置に設備を取り付ける、通路にもなるブリッジを吹き抜けに渡す、電球交換の不要なLED照明を採用する、といったことが有効です。
また、定期的にハウスメーカーに点検を依頼することで、専門家によるメンテナンスがしやすくなります。
これを防ぐためには、メンテナンスを考慮して、脚立で届く位置に設備を取り付ける、通路にもなるブリッジを吹き抜けに渡す、電球交換の不要なLED照明を採用する、といったことが有効です。
また、定期的にハウスメーカーに点検を依頼することで、専門家によるメンテナンスがしやすくなります。
2階のスペースが狭くなる
吹き抜けを設けることは、2階の床面積が減少することを意味します。しかし、必要な収納量を確保したり、個室のスペースを工夫したりすることで、快適に過ごすことができます。
これを防ぐためには、設計担当者と相談し、バランスの取れたプランを検討すると良いでしょう。
これを防ぐためには、設計担当者と相談し
音やにおいが室内に伝わりやすい
吹き抜けがあると、音やにおいが家中に広がりやすいというデメリットもあります。
音については、静かにしたい寝室などを吹き抜けから離したり、家族間で配慮したりすることで軽減できます。臭いについては、室内の換気を徹底し、適切な換気設備を設置することが重要です。
また、調湿性のある内装材を吹き抜け周辺に配置すると、においを吸着する効果も期待できます。音やにおいが広がってしまうことを防ぐには、これらを意識すると良いでしょう。
音については、静かにしたい寝室などを吹き抜けから離したり、家族間で配慮したりすることで軽減できます。臭いについては、室内の換気を徹底し、適切な換気設備を設置することが重要です。
また、調湿性のある内装材を吹き抜け周辺に配置すると、においを吸着する効果も期待できます。音やにおいが広がってしまうことを防ぐには、これらを意識すると良いでしょう。
耐震性などの強度に注意が必要となる
吹き抜け部分は構造上の支えが少ないため、地震などの揺れに弱くなる可能性があります。
これを防ぐためには、吹き抜けを設ける際に角に火打ち梁を入れたり、壁に耐力壁を入れたりして、十分な補強をおこなうことが不可欠です。
これを防ぐためには、吹き抜けを設ける際に角に火打ち梁を入れたり、壁に耐力壁を入れたりして、十分な補強をおこなうことが不可欠です。
ポラスの吹き抜け実例5選!
実例① 解放感のある吹き抜けの家
実例①は、足を踏み入れた瞬間その明るさにハッと息をのむことでしょう。その秘密は吹き抜けにあります。
天井を高く取り、縦の空間を最大限に活かすことで、驚くほど光が降り注ぎ、狭さを感じさせない開放感を演出します。開放型の大きなサッシとの相乗効果により、どこにいても広がりと明るさを感じることができます。
>>開放感のある吹き抜けの家はこちら
天井を高く取り、縦の空間を最大限に活かすことで、驚くほど光が降り注ぎ、狭さを感じさせない開放感を演出します。開放型の大きなサッシとの相乗効果により、どこにいても広がりと明るさを感じることができます。
>>開放感のある吹き抜けの家はこちら
実例② 自然光で明るい吹き抜けの家
実例②には、家族のつながりを育む大きな吹き抜けがあります。自然光が惜しみなく降り注ぎ、家全体を明るく開放的な空間に変えます。
高断熱高気密のツーバイシックス工法を採用しているため、広々とした吹き抜け空間でも冷暖房効率は抜群です。素早く快適な室温を保ちながら、省エネも実現します。
>>自然光で明るい吹き抜けの家はこちら
高断熱高気密のツーバイシックス工法を採用しているため、広々とした吹き抜け空間でも冷暖房効率は抜群です。素早く快適な室温を保ちながら、省エネも実現します。
>>自然光で明るい吹き抜けの家はこちら
実例③ 風と光を届ける吹き抜けの家
実例③の家では、各空間をつなぐ吹き抜けが、高い位置に設けられた窓から自然光をたっぷりととりこみ、心地良い風を家全体に通します。
白を基調とした明るい色彩と格子状の階段手すりが、光と風を各部屋に行きわたらせています。また、地域の風向きを考慮した独自の通風設計により、一年中快適な暮らしを実現しています。
>>風と光を届ける吹き抜ける家はこちら
白を基調とした明るい色彩と格子状の階段手すりが、光と風を各部屋に行きわたらせています。また、地域の風向きを考慮した独自の通風設計により、一年中快適な暮らしを実現しています。
>>風と光を届ける吹き抜ける家はこちら
実例④ 光と暮らす吹き抜けの家
実例④は、自然とデザインが融合したナチュラルモダンな家です。
その魅力は、大きな吹き抜けと鉄骨階段が創り出す、大胆かつ繊細な空間です。吹き抜けにより家全体に明るさと広がりを生みつつ、鉄骨でスタイリッシュな印象を感じさせます。
天井の木目貼りが温もりを添え、洗面やキッチンにあしらわれたタイルが空間に彩りを加えます。木のぬくもりを感じさせるデザインは、日々の生活を自然体で満たしてくれることでしょう。
>>光と暮らす吹き抜けの家はこちら
その魅力は、大きな吹き抜けと鉄骨階段が創り出す、大胆かつ繊細な空間です。吹き抜けにより家全体に明るさと広がりを生みつつ、鉄骨でスタイリッシュな印象を感じさせます。
天井の木目貼りが温もりを添え、洗面やキッチンにあしらわれたタイルが空間に彩りを加えます。木のぬくもりを感じさせるデザインは、日々の生活を自然体で満たしてくれることでしょう。
>>光と暮らす吹き抜けの家はこちら
実例⑤ 西海岸デザインの吹き抜けの家
実例⑤は、ディープブルーが映える、西海岸テイストのお家です。ポラスのモデルハウスのデザインを取り入れ、随所にこだわりが光っています。
大きな吹き抜けとワイドサッシが、空間に非日常的な解放感をもたらします。たっぷりの光が降り注ぐ明るいリビングは、まるで海外のリゾート地のような心地よさ。造り付けのTVボードなど、こだわりインテリアもポラスの大工の技術で実現します。
>>西海岸デザインの吹き抜けの家はこちら
大きな吹き抜けとワイドサッシが、空間に非日常的な解放感をもたらします。たっぷりの光が降り注ぐ明るいリビングは、まるで海外のリゾート地のような心地よさ。造り付けのTVボードなど、こだわりインテリアもポラスの大工の技術で実現します。
>>西海岸デザインの吹き抜けの家はこちら
吹き抜けをよりよく生かす設計の工夫
窓の性能や配置をよく検討する
吹き抜けの仕上がりを大きく左右するのが、窓の設計です。うまく配置することができれば、ほどよく風が流れ、明るい日差しに満ちた空間を実現できます。
そのポイントの一つが窓の断熱性能です。一般的な1枚ガラスのアルミサッシ窓は断熱性能が低く、夏は日射熱をそのまま取り込んで熱気がこもり、冬は結露でびしょびしょになってしまうことも…。
複層ガラスの樹脂サッシ窓のような断熱性能の高い窓を選ぶと、外気温の影響を受けにくくなります。
なお複層ガラスには、熱を取り込む日射取得型と熱を遮る日射遮蔽型の2種類があります。南には冬の日射熱を取り込む日射取得型、その他は熱の影響を抑える日射遮蔽型を選ぶのがセオリーです。ただし、窓の向いている方角や太陽高度、庇や軒の有無などの諸条件によっても設計内容は変わってくるので、設計担当者とよく話し合うことをおすすめします。
そのポイントの一つが窓の断熱性能です。一般的な1枚ガラスのアルミサッシ窓は断熱性能が低く、夏は日射熱をそのまま取り込んで熱気がこもり、冬は結露でびしょびしょになってしまうことも…。
複層ガラスの樹脂サッシ窓のような断熱性能の高い窓を選ぶと、外気温の影響を受けにくくなります。
なお複層ガラスには、熱を取り込む日射取得型と熱を遮る日射遮蔽型の2種類があります。南には冬の日射熱を取り込む日射取得型、その他は熱の影響を抑える日射遮蔽型を選ぶのがセオリーです。ただし、窓の向いている方角や太陽高度、庇や軒の有無などの諸条件によっても設計内容は変わってくるので、設計担当者とよく話し合うことをおすすめします。
吹き抜けの上下からエアコンを使う
吹き抜けは床から天井までの高低差が大きいため、冷暖房を効率よく機能させるには、エアコンの設置場所がカギになります。
例えば2階ホールと1階、といった具合に吹き抜けの上下に1台ずつエアコンを設けるというのもひとつの方法です。2階のエアコンは夏の冷房用に、1階のエアコンは暖房用とすれば、暖気は上に、冷気は下に流れる性質があるため、吹き抜け空間全体を効率よく快適なものにできます。
ただし、家全体の換気計画にも関わってきますので、具体的な配置については、設計担当者とよくご相談ください。
例えば2階ホールと1階、といった具合に吹き抜けの上下に1台ずつエアコンを設けるというのもひとつの方法です。2階のエアコンは夏の冷房用に、1階のエアコンは暖房用とすれば、暖気は上に、冷気は下に流れる性質があるため、吹き抜け空間全体を効率よく快適なものにできます。
ただし、家全体の換気計画にも関わってきますので、具体的な配置については、設計担当者とよくご相談ください。
耐震性を考慮して構造、間取りを決める
吹き抜けという大きな空間には、それを支える柱や筋交いを入れることが難しいため、そのままでは耐震性の低い場所になってしまいます。そのため、吹き抜けを設ける場合には、家全体のバランスを考慮し、耐震性を確保するための補強を適切に施すことが重要になります。
ポラスでは、全棟で構造計算を実施し、どの家でも弱点のない設計を目指しています。ポラス独自の「ウッド・イノベーターNEXT」という3Dシミュレーションによる検証を、実際に建築をするすべての住宅でおこない、大地震が起きた際の様子を確認のうえ、必要な補強をおこなうという仕組みです。
これらの取り組みにより、吹き抜けを設けても安心して暮らせる家になるのです。
>>ポラスの技術力について詳しく見る
ポラスでは、全棟で構造計算を実施し、どの家でも弱点のない設計を目指しています。ポラス独自の「ウッド・イノベーターNEXT」という3Dシミュレーションによる検証を、実際に建築をするすべての住宅でおこない、大地震が起きた際の様子を確認のうえ、必要な補強をおこなうという仕組みです。
これらの取り組みにより、吹き抜けを設けても安心して暮らせる家になるのです。
>>ポラスの技術力について詳しく見る
吹き抜けのある家ならポラスがおすすめ!
吹き抜けを設置することをご検討されているのであれば、さまざまな建築実例のあるポラスがおすすめです。多種多様な建築条件、お客様のご要望に対して、豊かな設計・施工ノウハウを駆使してご満足のいくご提案をしています。
また、吹き抜けのような立体的な空間を検討するなら実際にモデルハウスを見学しましょう。ポラスの住宅展示場や体感すまいパークで空間を体感すると、実践的なイメージをつかむことができます。
そこで生まれた疑問は、ぜひ住宅展示場内にいるポラスの営業担当者へおたずねください。さまざまな疑問についてサポートしてくれるはずです。また、モデルハウスをゆっくり見学したいときは事前のご予約がおすすめです。フェア開催期間は特に、予約の上のご来場で、素敵な特典がもらえることもあります。
ぜひ、お近くの展示場や体感すまいパークをご確認ください。
>>お近くの住宅展示場を見てみる
>>お近くの体感すまいパークを見てみる
また、吹き抜けのような立体的な空間を検討するなら実際にモデルハウスを見学しましょう。ポラスの住宅展示場や体感すまいパークで空間を体感すると、実践的なイメージをつかむことができます。
そこで生まれた疑問は、ぜひ住宅展示場内にいるポラスの営業担当者へおたずねください。さまざまな疑問についてサポートしてくれるはずです。また、モデルハウスをゆっくり見学したいときは事前のご予約がおすすめです。フェア開催期間は特に、予約の上のご来場で、素敵な特典がもらえることもあります。
ぜひ、お近くの展示場や体感すまいパークをご確認ください。
>>お近くの住宅展示場を見てみる
>>お近くの体感すまいパークを見てみる